

第34回(平成14年7月13日 於:熊谷高校)
テーマ:陰葉、陽葉の観察。 C4植物の葉の観察。 大豆の根粒の観察
参加者:阿部(上尾南高)、小林(熊谷高)、平岩(越谷南高)、森田(川越女子高)、加藤(熊谷高) 敬称略
<準備>
材料 陰葉、陽葉の観察…クスノキの葉、ツバキの葉
C4植物の葉の観察…スベリヒユの葉、トウモロコシの葉
大豆の根粒…大豆の根(種をまいて2週間ほど。草丈15cmほど。)
道具 カミソリ、ミクロトーム、ニワトコの髄、顕微鏡、スライドガラス、カバーガラス
<観察>
ともかく葉の切片を作らなくてはならない。カミソリを使って人の手の限界まで薄い切片を作ろうとしたが、クスノキやツバキなどの硬い葉では思うように薄い切片が作れない。そこでミクロトームの登場となった。やはりそこは機械。人の手で作る限界以上の薄い切片が楽々と作れてしまう。これなら初めから使えば良かった。
<結果>
陰葉、陽葉の観察
クスノキ、ツバキとも、日当たりの良い場所と悪い場所から葉を採取したが、季節的なこともあり、日当たりの良い場所は若い葉が多く、黄緑がかった色でやや軟らかいのに対し、日当たりの悪い場所は古い葉で、暗い緑色で硬かった。
陽葉は強光下で生育した葉なので、葉が厚く、柵状組織が発達しており、補償点が高く、気孔の数が多いという特徴を持つ。これに対して、陰葉は弱光下で生育した葉なので、葉が薄く、柵状組織の発達が悪く、補償点が低くて、気孔の数が少ないという特徴を持つ。
今回の観察では、クスノキの陽葉では柵状組織が2層で葉も厚めであったのに対して、陰葉では柵状組織が1層で葉も陽葉に比べてやや薄かったように見えた。ただし、ツバキではクスノキよりも若干違いが判りづらかった。やはりもう少し前から準備して、同じ葉齢の葉で比較できれば違いが顕著に見れたものと思う。

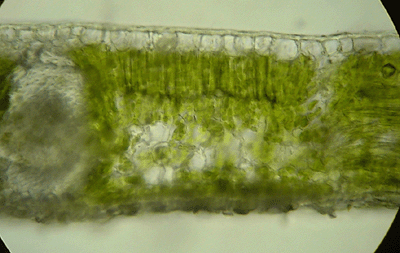
C4植物の葉の観察
スベリヒユは身近に生えているので入手しやすく、また葉が軟らかいのでミクロトームでなくカミソリでも切片が作れる。
スベリヒユの葉の切片を観察してみると、明らかに維管束の周りにある維管束鞘細胞が葉緑体を多く含み発達している。それに比べて葉肉細胞にはほとんど葉緑体を含まないので、葉の断面はランゲルハンス島ではないが、緑色の島が散在しているように見える。しかし、残念ながら維管束鞘の中心にあるべき維管束が細いためかその存在が良くわからない。
そこでトウモロコシでも観察してみた。こちらでは単子葉類独特の維管束がはっきりと見え、その周辺に維管束鞘細胞が葉緑体を多く含み発達しているのが良くわかった。
CAM植物(ベンケイソウ)の葉の観察
ちょうどベンケイソウも手元にあったので、ついでにCAM植物の葉の組織も観察してみることにした。この葉も軟らかいのでカミソリでも切片が作れる。顕微鏡で見てみるとなんとも不思議なつくりである。見た感じ、葉緑体を含む未分化な細胞が発泡スチロールのように集まって葉を形成している。これはCAM植物特有の構造なのか、あるいはベンケイソウ独自の物かは判らないが、そもそもベンケイソウは葉からも不定芽を出すほど全能性が強い植物なので、そのために葉においても細胞の分化があまり進んでいないのではないかと思う。
大豆の根粒の観察
まだ早いかとも思ったが、育てていた大豆に根粒がついたのでこれも観察してみた。種をまいてから2週間ほどだが、育ちの良いものには根粒があった。種をまいてから1週間目あたりでは見られなかったから何とか間に合った感じである。ちなみに大豆の根粒は土中に住むリゾビウムという根粒菌が根に共生したもの。であるから、対照に行った水耕栽培で育てた大豆には根粒が出来なかった。
これも根についた根粒を薄い切片にして観察したが、細胞内に根粒菌が存在している姿こそ見られなかったが、切片の周辺に内部から出てきたのであろう根粒菌が多数存在しているのが確認できた。
<反省>
今回は何となくとりとめのない観察になってしまった。特に陰葉と陽葉はしかっりとしたサンプルを作成して観察すべきであった。両者の違いが生育における光条件の違いのみであってこその陰葉と陽葉で比較してみるべきであった。もちろん今回のように日向と日陰から葉を採取しても、何となくの違いは確認できたが、明確な違いには至らなかったようにも思える。
Omnisサークル次回活動の予定
日時 10月19日(土)13:00
場所 埼玉県立越谷南高等学校 於生物室
テーマ
参加自由。希望者は連絡下さい。 ymorita@mb.infoweb.ne.jp