方法
1.卵と精子を得る。(omnisサークル(13)第13回参照)
2.1時間半から2時間ほど待って(水温によっても異なる)2細胞期になった頃に、ミキサーで5秒間程度粉砕する。

3.胚が沈むのを待って、海水を交換する。
4.あとは観察するだけ。
通常のウニの受精・発生をするときに、同時に用意しておけば、生徒にも観察させられると思います。
また、連続的に観察する場合は、次のようなシャーレを用意しておくと長い間観察できます。
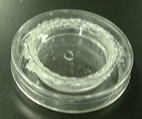
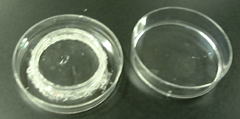
(1)大きさの違う、プラスチックシャーレを用意する。
(2)大きい方のフタに、小さい方の本体と同じ大きさの穴をあける(ホッとカッターがあると便利。無ければはんだごてなどで)。
(3)二つを張り合わせる。溶かしてうまくくっつける。大きさが合わなければ、余ったプラスチックを溶かしてつなげる。
(4)こんな風にして使う。

×10の対物レンズまで使うことができる。
※ ×4倍なら、こんなことをしなくても普通の小型シャーレで観察できるが、フタに水滴が付くと見えなくなってしまう。
このシャーレは、くぼんだ部分が水没しているので、曇ったりすることはない。
倒立顕微鏡があれば、こんな苦労はないのだが、一般の高校に倒立顕微鏡はない。
培養細胞の観察などにも応用できる。
×40の対物レンズを使用するときは、くぼんだ部分(小さいシャーレの部分)にカバーグラスよりも一回り小さく穴をあける。そこにグリースでカバーグラスを貼り付ければ観察できる。ただし、大きい方のシャーレ本体を削って、高さを厳密に調整する必要がある。また、カバーグラスを接着剤などで接着させると、膨張率の違いから、はずれてしまう。
結果
それらしい段階のものを撮りました。
しかし、それぞれおなじ胚をおっているわけではありません。みんな別々のものです。








 反射光で撮ってみました。
反射光で撮ってみました。



